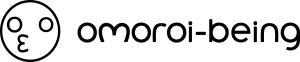Postsomoroi-being記事
音楽博士Dr. Capitalと考える関西音楽の魅力
~なぜ関西人は幸福度が高いのか?音楽博士Dr. Capitalが『オモロイ』文化と音楽の関係性を深堀~
ライター:河越ゆり

音楽から関西の幸福感を紐解く
- 先日、omoroi-beingが行った独自調査で、「関東よりも関西の方が、幸福度が高い」という興味深い結果が出た。
【参考レポート】
博報堂DYホールディングス「これからの幸福感」プロジェクト「はたらく世代の幸福感調査(関東・関西編)」を実施 | 関西のオモロイ情報を発信する「omoroi-being(オモロイ ビーング)」「本音・共鳴・シェア」のある生活習慣が幸福度を高める要素として導き出されたが、この「共鳴」と「シェア」の裏側には、関西特有の「音楽の楽しみ方」も影響しているのではないかと推察。
このテーマを掘り下げるべく、アメリカ出身大阪在住の音楽博士Dr. Capital氏にインタビューを実施。
音楽博士としての専門的な視点と、アメリカ出身という客観的な視点から、音楽と幸福の関係性、関西の音楽の魅力について語ってもらった。 
抑圧された感情を、音楽が解放する
Dr. Capital氏は「幸福」の定義を非常にシンプルに語った。
「ぼくが思う『幸せ』とは、ストレスがなくて、したいことができる状態のこと。でも大人は社会のルールとか、人の目を気にして『恥ずかしい』って感情を持つでしょう?言いたいこと、したいことを我慢してしまう。感情を抑えていること自体が不幸ではないけど、それがストレスだったら、不幸に繋がるんじゃないかな」
この『恥ずかしさ』や『我慢』による感情の抑圧が、幸福な状態を遠ざける大きな要因だと指摘。
「大人って、どんな感情も抑えようと頑張りますよね。でも、音楽はそういう感情を、ワッと動かしてくれるんです。結婚式でもお葬式でも、みんな涙を抑えているところに音楽が始まって、涙が流れる。失恋した時だって、『あの曲』を聞いて泣かせてくれる。音楽って、この抑えている感情のストレスを解消してくれる、すごく重要な役割を持っています」
それが顕著に表れるのが、ライブ会場だ。
「ライブ会場も、日常の社会ルールとは違う、特別な空間なんですよ。電車の中じゃできない『踊る』『大声を出す』が、ライブでは許される。みんな、音楽を通して『自由に、やんちゃになってもいいんだ!』っていう気持ちになり、ストレスから解放されることを味わえるのだと思います」
型破りな音楽を自由に、関西らしく楽しむ
関西出身の友人やアーティストの知り合いの多いDr. Capital氏は、関西の音楽についてこう語る。
「印象的な音楽やアーティストには、型にはまろうとするのではなく、型を壊そうとする、反抗的なところがありますね。面白いことや新しいことをするのがクリエイター。考え方が自由だと、作品も面白くなる。関西のアーティストには、お笑いの影響もあってか、かなり面白い方がたくさんいます。最初に関西のアーティストで印象的だと思ったのが、ウルフルズ。96年に初めて来日した時、「ガッツだぜ」のMVがすごい面白くて、元気で自由でロックっぽくて、関西らしさを感じました。すかんちのローリー寺西さんとか、ブルースバンドの憂歌団とかも遊び心がすごくあって楽しいし、以前一緒に音楽制作をしていた関西出身のDJ NOZAWAさんも歌詞の中にコントいれるなど、クリエイティブで面白いことを沢山していました」

ウルフルズ ガッツだぜ!!MVより(https://www.youtube.com/watch?v=ATU0gXzMsLw)
最も関西らしさを感じるのは、ライブ会場での様子だという。
「東京でライブしても、みんな笑って、手拍子して、踊ってくれて、すごく楽しく盛り上がる。大阪は、それがさらに騒がしく、賑やかになる感じがします。特にMCの際にはお客さんが会話っぽく突っ込んでくれたりと、東京以上に自由自在な空間になることが多い気もしています」
こうしたライブ文化は、心から(本音で)音楽を楽しみ、周りの人と分かち合う(共鳴・シェアする)という、omoroi-beingが考察する幸福感の要素と深く重なり合うように感じられる。
「自由に、やんちゃになってもいい」という音楽の解放感と、「みんなで楽しむ」という価値観が融合し、自ずと幸福感のサイクルをより豊かに回しているのではないか。
また、意外なところでは、日本の伝統芸能である「文楽」にも関西の音楽らしさを感じるという。
「文楽のナレーターのしゃべりが面白くて、メロディックで笑うところも沢山あるし、ジョークもある。文楽の語り(義太夫)が関西弁であることに後から気づいた時は、すごい衝撃でした。これもまさに、伝統音楽の中にある関西らしさだと思います」
「面白く自由に」という精神が、音楽のジャンルを問わず関西文化に深く息づいているようだ。
関西弁にも潜む幸福のメカニズム
Dr. Capital氏は、関西弁に独特の柔らかさ、リラックス効果を感じているようだ。
「例えば、『いいだろう』という標準語の『いい』という母音は、高音の倍音が強調され、縦の堅い印象に聞こえる。それに対して、関西弁の『ええやろ』はもっと柔らかくて、言いやすくて、周波数の分析をしても、高音の倍音が比較的強調されない響き。『だろう』の『だ』という濁音も堅い子音で、『だ』より『や』の方が柔らかい印象をもたらしてくれる。日本語母語の皆様にどう聞こえるか分かりませんが、僕にとって関西弁は聞こえ方としてストレスが少ない、滑らかさ、リラックス感があるように感じます」
また、方言は「標準語」という括りを超えることで、クリエイティビティが発揮されているという。
「『標準語』という言葉が、『これ以外は標準じゃない』という硬いカテゴリーをつくるじゃないですか。方言はそういう硬いカテゴリーじゃないからこそ、クリエイティビティとか自由さ、楽しさに繋がっているんだと思う」
方言には、音色そのもののリラックス効果や親しみやすさ、また『標準語』という規範に縛られない自由度が内包されていることが伺える。
こうした言語的な特徴、すなわち「日常的なリラックス効果」と「自由な表現の許容」も、関東圏よりも関西の幸福度を底上げしている一因なのかもしれない。
言葉に含まれるリズムとメロディは、音楽に「おもしろさ」を加えているという。
「『来てください』と『切ってください』では、リズムが全然違うじゃないですか。だから、言葉のリズムが音楽とすごく似ている。イタリア語もいい例ですよね。『ピッザ』みたいに抑揚があってメロディック。そのメロディの長さとか、音の上がり下がりが、音楽を面白くしてくれている」
Dr. Capital氏との対話を通じて、型にはまらず音楽に親しむこと、そして身近な「言葉」を遊び心を持って使ってみることが、日常を豊かにする秘訣のように見えてきた。
「面白いことは、人をハッピーにするからね」
Dr. Capital氏の哲学は、omoroi-beingが追求する「オモロさ」と「幸福」の価値観に鮮やかな説得力を与えてくれた。
- 【Dr. Capital氏のプロフィール】
アメリカ・オレゴン州ポートランド生まれ。音楽博士号をアメリカで取得した音楽表現効果の専門家。J-POPを深く研究し、現在は関西在住のアーティストとして活動する傍ら、人気YouTuberとして関西弁で音楽理論の解説などを発信している。